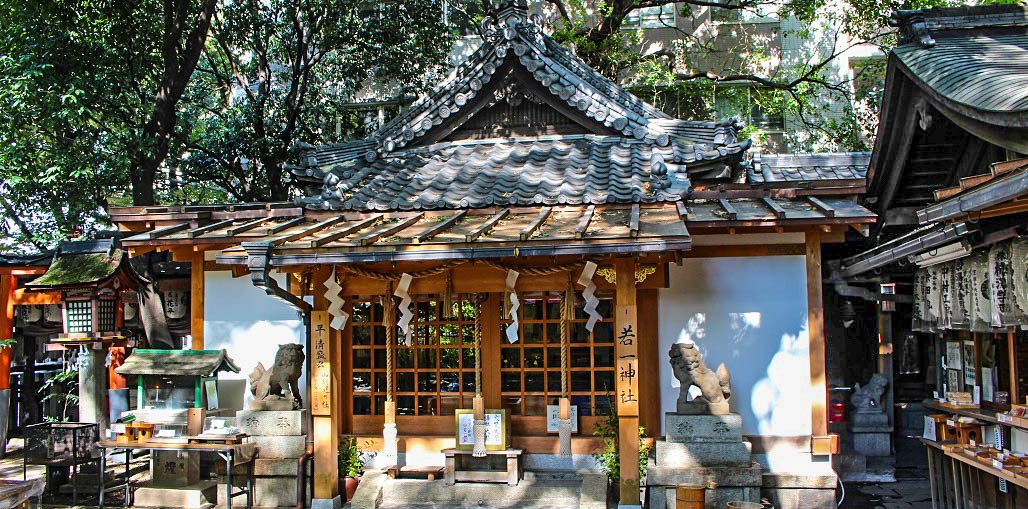京都駅周辺
道祖神社
大通院
即宗院
臨済宗東福寺派、大本山東福寺塔頭。嘉慶元年(1387)九州薩摩藩島津氏久公が、剛中玄柔禅師(東福寺第54世住持)を開山として建立。 薩摩藩の菩提寺で氏久公の法名「齢岳玄久即宗院」から寺名とした。 創建当時は現在より南に位置していたが、永禄12年(1569)に火災で焼失し、島津義久公が慶長18年(1613)頃再建した。 その地は、関白藤原兼実公が晩年営んだ山荘「月輪殿」の跡で、国宝「法然上人絵伝」にも描かれている。 寛政11年(1799)発行のガイドブック「都林泉名勝図絵」にも名園として紹介されている。 庭園は現在京都市名勝に指定され、紅葉の美しさと千両の鮮やかさで有名である。 西郷隆盛公と僧月照(京都清水寺の勤皇僧)は、王政復古を志し、新撰組や幕府の追っ手を逃れこの即宗院の採薪亭で幕府転覆の策をめぐらした。 西郷隆盛公はその後の苦難を乗り越え、鳥羽伏見の戦い(慶応5年)から勝ち進み勝利を手中にした。 戦いの戦死者524霊を弔うためこの即衆院で斎戒沐浴し碑文を書きしたため、明治2年に「東征戦亡の碑」を建立した。 また、篤姫が、近衛家の養女となって徳川家へのお興しいれの際、この即宗院に立ち寄ったと言われる。
菊姫稲荷神社
福田寺
新善光寺
来迎堂(らいこうどう)と号する浄土宗の寺である。 本尊の阿弥陀如来像は、善光寺(長野県)の創建者である本田善光の子、義助によって善光寺の阿弥陀如来像の分身像として造られたものと伝えられている。 当初、この仏像は、南都(奈良県)にあったが、天仁2年(1109)に、堀川松原の地に伽藍が建立され、そこに安置された。 以後、来迎堂新善光寺と呼ばれ、多くの帰依者を集めた。 しかし、応仁の乱後、兵火に遭い、寺地も転々とし、天正19年(1591)、豊臣秀吉の命により現在の地に移された。 江戸時代には、幕府より御朱印の寺領を受け、天下泰平、国民安全の御祈祷所として栄えたが、天明・元治の大火で類焼してしまった。 現在の堂宇は、その後に再建されたものである。
市中山 最勝王院 金光寺
時宗。山号、市中山は、平安京の東の市に有った事に由来する。 空也上人が松尾大社の神勅に依り、松尾社前の鰐口半分を頂き、鉦たたき念仏の道場として市屋道場のもとを創建したと伝えられる。 本尊引接阿弥陀如来は定朝作といわれ、花山天皇の御念持佛を空也上人が受けたと伝えられる。もと天台宗であったが、鎌倉期32代唐橋法印胤恵が一遍に帰依し、作阿弥陀佛(作阿)と名を改め時宗とした。 その所在地から市屋道場と呼ばれ、大永年間(1521~1528)には足利義晴が泊ったことから、一夜道場とも呼ばれた。 市の祭神、市姫神社を鎮守とし保護する。 1591年(天正19)豊臣秀吉の行なった京の街の区画整理で、市姫社と共に現在地に移転した。